本展はイギリスのヴィクトリア&アルバート博物館の所蔵作品を中心に、19世紀後半の耽美主義(唯美主義)を代表する絵画や本の挿絵、工芸品、宝飾品など約140点を紹介した展覧会。2011年にヴィクトリア&アルバート博物館で開催された『The Cult of Beauty: The Aesthetic Movement 1860-1900』を日本向けに新たに構成しなおしたということです。
英語のタイトルは『Art for Art’s Sake (芸術のための芸術)』。芸術至上主義、美のための美を追求したイギリスの唯美主義の美術にスポットを当てた総合的な展覧会としては日本初なのだとか。
序
19世紀半ばの美術やデザインの世界はさまざまな形式や理論が入り乱れていて、そこに「ひとつの明確で革命的な理想」として現れたのが“唯美主義”であると会場の説明にありました。
ウィリアム・ド・モーガン 「大皿」
1888年頃 ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館蔵
1888年頃 ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館蔵
唯美主義の芸術家やパトロンの邸宅を飾ったのがこうした工芸品で、それは必需品であり、ステータスであったようです。ヒマワリや孔雀は唯美主義のシンボルとして、いろいろな作品にたびたび登場します。
エドワード・バーン=ジョーンズ 「ヘスペリデスの園」
1882年 ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館蔵
1882年 ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館蔵
バーン=ジョーンズの「ヘスペリデスの園」は装飾性が高く、なんともゴージャスな作品。表面は浅浮彫りで細工され、仕上げに金と白金の箔が貼られています。
新たな美の探求
『ラファエル前派展』を観てきた流れで考えると、ロセッティやミレイあたりが唯美主義の原点なのかなとばかり思っていたのですが、そうした前衛の画家だけでなく、正統派の画家の中でも伝統的な主題にとらわれず、フォルムや色彩の美を追求した唯美主義者がいたとありました。ワッツやフレデリック・レイトンがその代表的な画家のようです。
ジョージ・フレデリック・ワッツ 「孔雀の羽を手にする習作」
1862-65年頃
1862-65年頃
ワッツというと象徴主義の代表作「希望」を思い浮かべますが、もともとはイタリア・ルネサンスに影響を受けだ画家だそうで、この「孔雀の羽を手にする習作」は白く柔らかな肉感の中にも美しさや色気が前面に出ていて、古典的な女性像にはない官能性が際立っています。会場の解説に「女性を単に美の対象として見るのではなく、モデルの性的な魅力を率直に楽しむように描いた」ということが書いてあったのですが、この辺りから裸婦画に性的な意味が盛り込まれるようになったということなんでしょうか。
そのほか、レイトンの「パヴォニア」やロセッティの「愛の杯」がとても印象的。ロセッティによる装幀や挿絵なども展示されています。
遠い過去、遥かなる場所Ⅰ ジャポニス
遠い過去、遥かなる場所Ⅱ 古代文化という理想
唯美主義の芸術家やデザイナーは当時ヨーロッパでブームになっていたジャポニスムや、また古代ギリシャ美術をイメージソースにした作品を発表します。
勉強不足だったんですが、“アングロ・ジャパニーズ”という様式を始めて知りました。日本美術や特に浮世絵の色彩やデザインに影響を受けたインテリアや家具デザインのことで、多様な装飾的要素を組み合わせ、形態の軽快さや美しさにポイントを置いていたということです。ゴドウィンの装飾デザインや生地見本帳、ホイッスラーによる花瓶など、日本的なものにヨーロッパの美的センスが融合していて興味深いものがあります。
アルバート・ムーア 「黄色いマーガレット」
1881年 郡山美術館蔵
1881年 郡山美術館蔵
フレデリック・サンズ 「メディア」
1866-68年頃 バーミンガム美術館蔵
1866-68年頃 バーミンガム美術館蔵
ムーアの「黄色いマーガレット」は古代ギリシャの女性像を彷彿とさせつつも、写実的な質感と色彩が陶然とするほどの美しさ。「メディア」はサンズの代表作とのこと。メディアのドラマティックで呪術的要素が伝わってきます。ほかに、アルマ=タデマのデザインによる腕輪や肘掛け椅子も見もの。
唯美主義運動とグローヴナー・ギャラリー
唯美主義のサロン的な役割を果たしたロンドンのグローヴナー・ギャラリーに所縁の作品を展示。縦に細長いキャンバスに女性の全身を彫像のように描き、まわりに花をあしらったムーアの「花」がここでも素晴らしい。
ウィリアム・ブレイク・リッチモンド 「ルーク・アイオニディーズ夫人」
1882年 ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館蔵
1882年 ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館蔵
フレデリック・レイトン 「母と子(さくらんぼ)」
1864-65年頃 ブラックバーン美術館蔵
1864-65年頃 ブラックバーン美術館蔵
≪「美しい人々(上流人士)」と唯美主義の肖像画≫では、リッチモンドの「ルーク・アイオニディーズ夫人」とレイトンの「母と子(さくらんぼ)」が秀逸。リッチモンドの衣装の質感やレイトンの百合やサクランボの写実を超えた美しさには目を見張ります。「ルーク・アイオニディーズ夫人」には背景に手の込んだ刺繍が施された日本の絹地が、「母と子」には鶴の屏風が描かれ、ともに当時のジャポニスム・ブームがいかにヨーロッパの生活に受け入れられていたかがよく分かります。
エドワード・バーン=ジョーンズ 「ブローチ」
1890年頃 ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館蔵
1890年頃 ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館蔵
バーン=ジョーンズのデザインによるトルコ石や珊瑚、真珠、ルビーを象嵌したブローチや、象牙と黄水晶を象嵌したブローチなど、女性でなくとも綺麗だなと思う作品がズラリ。
ホイッスラーとゴドウィン
モリスやホイッスラーと関係の深かった建築家ゴドウィンによるデザイン建築図やデザイン画から飾り戸棚やテーブルまで、またホイッスラーのエッチング作品などを展示しています。ちなみに、出品リストでは≪唯美主義運動とグローヴナー・ギャラリー≫の前にあるのですが、実際にはそのあとに展示されています。
ジェームズ・マクニール・ホイッスラー 「ノクターン: 黒と金-輪転花火」
1875年 テイト蔵
1875年 テイト蔵
グローヴナー・ギャラリーに展示されたホイッスラー作品を、かつてラファエル前派を高く評価していた評論家ラスキンが酷評したことがきっかけで裁判沙汰になります。「ノクターン: 黒と金-輪転花火」はそのとき展示されていたホイッスラー作品の一枚。当時ホイッスラーは夜景の闇と花火などの瞬間的な光の美しさに強い関心を示し、類似の作品を多く残しているようです。ちなみに、ホイッスラーは勝訴するも裁判費用のため破産してしまったのだとか。
テムズ川、ヴェネチア、アムステルダムをそれぞれ描いたホイッスラーのエッチングもとても印象的でした。
「ハウス・ビューティフル」
唯美主義の絵画芸術の盛り上がりとともに、室内装飾への関心が高まったといいます。ここでは当時の室内装飾の様子を絵画やデザインから観ていきます。
アンナ・アルマ=タデマ 「タウンゼンド・ハウス 応接間、1885年9月10日」
1885年 ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ蔵
1885年 ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツ蔵
まず目を見張るのは、アンナ・アルマ=タデマの「タウンゼンド・ハウス 応接間」。アンナ・アルマ=タデマはイギリスを代表するヴィクトリア調時代の画家ローレンス・アルマ=タデマの娘で、本作はローレンスの自宅兼アトリエを描いたもの。なんとアンナが17歳のときの作品だそうです。父譲りの精緻で写実的な美しい作品。調べても検索に引っかからないので、画家としては活躍しなかったのかもしれませんが、「才能あるアマチュア画家」とパネルで解説されていた通り、恐るべき才能の持ち主だったようです。
ウォルター・クレイン 「奥方の部屋」
1881年頃 スティーブン・キャロウェイ・コレクション
1881年頃 スティーブン・キャロウェイ・コレクション
アーツ&クラフツとも関わりの深い挿絵画家クレインの「奥方の部屋」も素敵です。当時の最先端のお洒落な生活って、こんなだったんでしょうね。
「美術産業製品」 -唯美主義のデザイナーと営利主義
さて、一つ階を降りて2階の会場へ。
ここではクレインがデザインを手がけた壁紙やバーン=ジョーンズのお皿、ケイト・グリーナウェイやド・モーガンのタイルなど、色彩や模様の美しさが素晴らしい当時の商業製品を展示。ウィリアム・モリスの「家には役に立つと思うか美しいと信ずるもの以外置かないように」という言葉に、自分の家の中を見渡してしまいました(笑)
オスカー・ワイルド、唯美主義運動と諷刺
ここでは唯美主義の象徴として、時代の寵児となったオスカー・ワイルドの本の装幀やビアズリーによる挿絵、また当時の唯美主義者を揶揄した風刺画などが展示されています。
ワイルドは作品の内容が物議を醸すなど常に注目を集めいていたのは知られていますが、当時は唯美主義者そのものが不健全とか変人扱いされていて風刺の対象になっていたということは知りませんでした。しかし、ワイルドの名が唯美主義と同義語になっていたことが災いし、アルフレッド・ダグラスとのスキャンダルでワイルドが身の破滅を招くと、唯美主義の人気も評価も失墜してしまったといいます。
オーブリー・ビアズリー 「クライマックス -サロメ」
1907年(1894年初版) ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館蔵
1907年(1894年初版) ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館蔵
ワイルドの享楽的で扇情的な作風とビアズリーの耽美的で画風は、その時代の退廃的な、デカダンスなムードと相俟って、唯一無二の組み合わせだったのだなと強く感じます。
シメオン・ソロモン 「月と眠り」
1894年 ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館蔵
1894年 ヴィクトリア・アンド・アルバート博物館蔵
『ラファエル前派展』でも気になっていたソロモンも数点展示されていました。いま観るとそれなりに評価ができると思うのですが、当時はこの同性愛的な表現はどう受け取られていたのでしょうかね。
輝かしい落日 -唯美主義後期の絵画と「ニュー・スカルプチャー」
最後に19世紀末の絵画や写真、また彫刻を紹介しています。本展のメインビジュアルに使われているムーアの「真夏」はここに登場。鮮やかなオレンジ色の衣装とマリーゴールドの花環、またシンメトリーな構図がとても印象的です。ムーアの作品は「主題をもたない」と評されていますが、この絵に意味するものはなくとも、芸術のための芸術、美の極致を描こうとする確固とした意思は伝わってきます。
アルバート・ムーア 「真夏」
1887年 ラッセル=コート美術館蔵
1887年 ラッセル=コート美術館蔵
19世紀後半のイギリスの芸術運動をただ絵画の側面だけで見るのではなく、美術工芸品も含めその特色を探るという意味で非常に興味深い展覧会でした。会場の三菱一号館美術館は英国人建築家ジョサイア・コンドルが設計(明治27(1894)年に竣工)したもので、19世紀末の英国的な雰囲気を今に伝える空間でこれらの芸術作品を鑑賞できるというのもプラスだと思います。
【ザ・ビューティフル -英国の唯美主義 1860-1900】
2014年5月6日まで
三菱一号館美術館にて
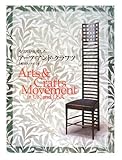 モリスが先導したアーツ・アンド・クラフツ―イギリス・アメリカ
モリスが先導したアーツ・アンド・クラフツ―イギリス・アメリカ もっと知りたいバーン=ジョーンズ―生涯と作品 (アート・ビギナーズ・コレクション)
もっと知りたいバーン=ジョーンズ―生涯と作品 (アート・ビギナーズ・コレクション) オーブリー・ビアズリー
オーブリー・ビアズリー





















































![月刊 美術 2014年2月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51Yq%2BxUYUsL._SL160_.jpg)
